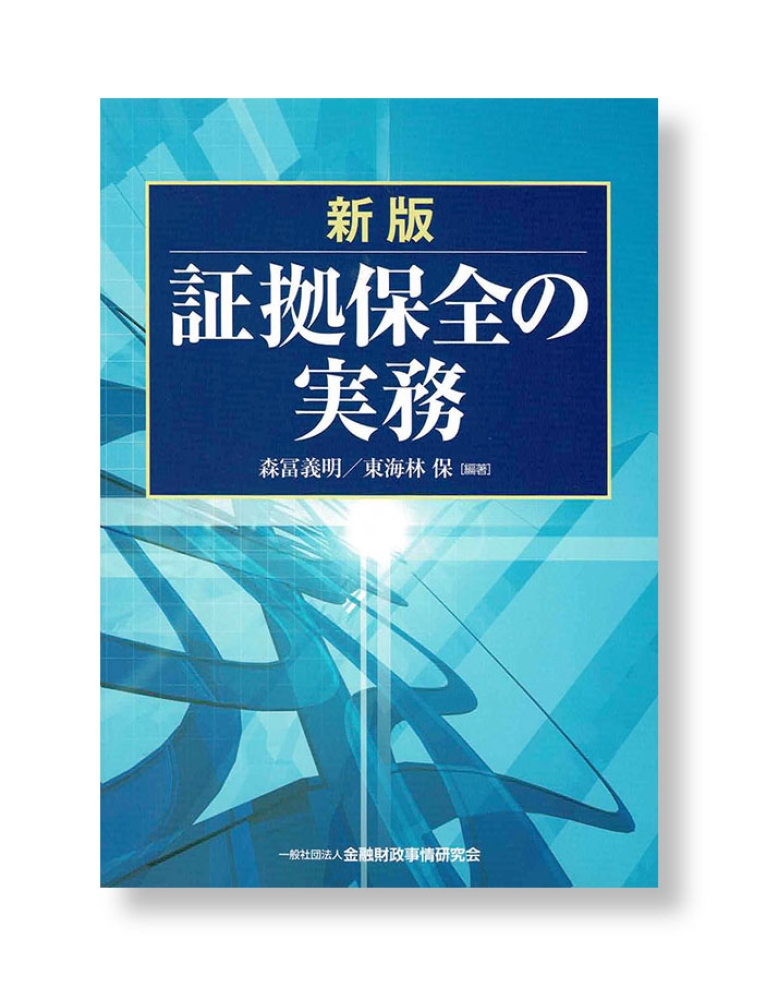
一般社団法人 金融財政事情研究会出版の書籍 証拠保全の実務
裁判所の証拠保全の現場で、代理人弁護士だけではなく、書記官、時には裁判官も本書を携行しているのを見かけます。検証が開始される前に若い書記官が本書を目を皿のようにして読んでいるのを見て、今日の検証は大丈夫かなと不安を打ち明ける弁護士さんもいました。いずれにしても証拠保全についての体系的な解説書は本書しかないらしく、現場では皆さん証拠保全のバイブルと呼んでます。カメラマンとして証拠保全に携わる自分としても、本書の概要くらいは共有できるようにと拝読しました。
自分が読んだのは2015年版ですが、カメラマンと写真に関する部分にずっと違和感を感じてました。自分は法務の専門家ではありませんが、この10数年で100件程カメラマンとして現場に立ち会った経験から、その気になった点をについて記載してみたいと思います。
本書ではデジタルカメラの存在に触れてはいますが、本書の架空の物語部分、解説のカメラマンによる撮影は全てフィルムカメラ使用で記述されてます。自分の経営する写真撮影プロダクションは1999年よりデジタルカメラを本格的に導入して2002年には全ての撮影をデジタルでのワークフローに置き換えました。プロカメラマン全般を見ても2005年以降は特殊な用途を除いて全てデジタルカメラによる撮影が一般的にになっていたと思います。自身も証拠保全の記録は初回より全てデジタルカメラによって撮影してます。
フィルムカメラによる撮影の場合、装填するフィルムはカラーかモノクロ(白黒)以外にも用途によって、文書等の線画にはハイコントラスト用、精密描写には微粒子、中間調重視には多階調、光量の少ない場所では高感度、など各種専用フィルムを使い分ける必要がありました。プロ用のデジタルカメラによる撮影の場合は、撮影時に被写体のすべての情報をそのままデータ(Rawデータ)として記録し、専用の現像ソフトで用途に応じたデータ(例 JPG)に書き出す方式です。よって、撮影時に環境の光量による感度だけを設定(ISOの設定)さえすれば、本書の物語のようにカラーと白黒を分けて撮影する必要はありません。現場で裁判官より、今撮影してるのはカラーか白黒かと聞かれたことがありますが、本書を参照して確認されたのかもしれません。
また、注意点として、プロカメラマンがデジタルカメラを使う場合、撮影データを誤消去する可能性があると記載されている箇所がありますが、プロカメラマンの場合、撮影データは2枚のメディアに同時に記録するなどデータの冗長性を確保しているので、その心配はまずありません。むしろフィルムカメラの方が物理的なフィルム面の傷、静電気によるスクラッチ、撮影後の現像のトラブルなど問題をゼロにはできませんでした。
検証後の調書作成時に撮影の順番についての記載もありますが、Rawデータには撮影年月日、時間が秒単位で同時記録されるので、検証時の流れを時系列で追うことが可能です。書記官によっては検証開始時から許可を得てボイスレコーダーで流れを記録されている場合があるので、事後の照合が容易になります。
以上、現在の現場ではフィルムでの撮影は行われない点を中心に、プロ用デジタルカメラによる撮影のメリットを説明させていただきました。